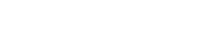会社概要
青森県八戸市鮫町下手代森2-1Google Map
事業紹介

主な漁場としては、太平洋近海、日本海近海、東シナ海となっている。10t未満の小規模な船から300tクラスの大規模な船までが日本近海で操業している。
大規模になると漁場を探索する探索船、網を投入する網船(本船)、漁獲物を運ぶ運搬船が1~2隻の計3~4隻が船団となり操業する。1船団(1カ統)の乗組員は約50名。漁獲量が多く重要な漁業の一つである。当社は、次世代型大中型まき網本船(運搬機能を併せ持つ網船)と探索機能を併せ持つ運搬船との2隻体制(ミニ船団)約34名で操業する。
※第八十三惣寶丸船団、第八十八惣寶丸船団はこのまき網漁法にて魚を漁獲する。
大きな群れをつくり回遊しているマグロ、カツオ、 アジ、サバ、イワシなどの魚群を、一枚の大きい帯状の網で包囲して、網の下の口を締めてから、次第に網を縮小してとる漁法。 主な漁場としては、太平洋近海、日本海近海、東シナ海となっている。10t未満の小規模な船から300tクラスの大規模な船までが日本近海で操業している。 大規模になると漁場を探索する探索船、網を投入する網船(本船)、漁獲物を運ぶ運搬船が1~2隻の計3~4隻が船団となり操業する。1船団(1カ統)の乗組員は約50名。漁獲量が多く重要な漁業の一つである。 当社は、次世代型大中型まき網本船(運搬機能を併せ持つ網船)と探索機能を併せ持つ運搬船との2隻体制(ミニ船団)約34名で操業する。
※第八十三惣寶丸船団、第八十八惣寶丸船団はこのまき網漁法にて魚を漁獲する。

船を一定の場所に鐘で留めておき、網を引き寄せる小規模なものから船を移動させながら網を引く方法の二つがある。
底曳網は海底により名称が異なり、(1)東シナ海で魚をとる底曳は二隻曳網、(2)北部太平洋を主な漁場とする沖合底曳網、(3)北西太平洋、アフリカ沿岸、ニュージーランド沖で漁獲する遠洋底曳網、(4)南氷洋でオキアミを漁獲するオキアミトロールに分別される。
※第六十八惣寳丸は沖合底曳網漁法となる。
※主な対象魚種は、イカ、タラ類、カレイ類、キンキ、ホッケ、他。
海底に生息している魚を、2本の引き網がついた大きな袋状の網を引いて漁獲する。 船を一定の場所に鐘で留めておき、網を引き寄せる小規模なものから船を移動させながら網を引く方法の二つがある。 底引き網は海底により名称が異なり、(1)東シナ海で魚をとる底引きは二隻引き網、(2)北部太平洋を主な漁場とする沖合底引網、(3)北西太平洋、アフリカ沿岸、ニュージーランド沖で漁獲する遠洋底引網、(4)南氷洋でオキアミを漁獲するオキアミトロールに分別される。
※第六十八惣寳丸は沖合底引網漁法となる。
※主な対象魚種は、イカ、タラ類、カレイ類、キンキ、ホッケ、他。
沿革
大型底曳網減船1隻
310トン型まき網運搬船「第十六惣寶丸」竣工
329トン型まき網本船「第八十三惣寶丸」竣工
まき網3カ統、沖底1隻体制となる279トン型まき網本船「第六十三惣寶丸」竣工
380トン型まき網運搬船「第十七惣寶丸」竣工